前の10件 | -
私家本 [Wessay]
どうしようか迷っていたのですが、頼んでみました、ブログの製本化。
「宝永町248番地」を”本”という形にしてみました。
ブログにアップした内容そのままに版下ができあがりますが、
対象とする記事をマイカテゴリーによって選別することができます。
記事を一時的に非公開にすることでも製本対象外にすることができます。
それから、まえがきやあとがきを追加したり、目次の形式も調整できるので
一般の小説のような構成にすることができます。
さらに、製本イメージ抽出後に本文の修正も可能なので、どうとでも編集可能です。
ブログ特有の空白行をなるべく削ったのですが、それでも300ページを超えました ^^;
装丁や文字フォント、縦書き横書きなどを指定することで”本”としての体裁も変えられますが、
一番シンプルな構成にしてみました。
10冊で頼むと、こんな荷姿で届きます。

「貴重品」なんていう荷札が付いていたのはちょっと大袈裟でしたが・・
表紙はこんな感じに指定しました。(デザインは何種類もありました)

本文や目次はこんな感じです。

フォントも文庫本で一般的な教科書体。
背表紙もちゃんと印刷されてきます。

出版するのではなく、自費出版でもなく、自分用に製本した本を私家本といいます。
宝永町248番地の登場人物にも断りなしに無理やり送りつけました(笑)
アナログな形に残すってのはいいですね。触れますからね。
オマケ

タマが二匹!!
「宝永町248番地」を”本”という形にしてみました。
ブログにアップした内容そのままに版下ができあがりますが、
対象とする記事をマイカテゴリーによって選別することができます。
記事を一時的に非公開にすることでも製本対象外にすることができます。
それから、まえがきやあとがきを追加したり、目次の形式も調整できるので
一般の小説のような構成にすることができます。
さらに、製本イメージ抽出後に本文の修正も可能なので、どうとでも編集可能です。
ブログ特有の空白行をなるべく削ったのですが、それでも300ページを超えました ^^;
装丁や文字フォント、縦書き横書きなどを指定することで”本”としての体裁も変えられますが、
一番シンプルな構成にしてみました。
10冊で頼むと、こんな荷姿で届きます。

「貴重品」なんていう荷札が付いていたのはちょっと大袈裟でしたが・・
表紙はこんな感じに指定しました。(デザインは何種類もありました)

本文や目次はこんな感じです。

フォントも文庫本で一般的な教科書体。
背表紙もちゃんと印刷されてきます。

出版するのではなく、自費出版でもなく、自分用に製本した本を私家本といいます。
宝永町248番地の登場人物にも断りなしに無理やり送りつけました(笑)
アナログな形に残すってのはいいですね。触れますからね。
オマケ

タマが二匹!!
宝永町248番地 第73話 [Wessay]
薄荷パイプ
その日はあっけなくやってきた。
学校から帰ってきて二階へかけあがり、靴脱ぎ場からランドセルを
部屋の中に放り込もうとしたら、お母ちゃんがいるのに気がついた。
「あれっ?おかえり」
「ただいま」
ぼくはじいちゃん子だったので、お母ちゃんに飛びつきはしなかった。
どうしていなくなったのか、聞いてみることすらしなかった。
何もなかったんだと思い込もうとしたのかもしれない。
そうであってほしいという願いのような気持ちはあったと思う。
だったら最近のことはすべてなかったことにすればいいのに、
ぼくの口は勝手に開いていた。
「この間、どろぼうがはいったんだよ」
「あら、そう」
「壁とね、レジを壊してね、お金を盗んでいったんだよ」
「それはこわかったねぇ」
「ううん、だれもね、気がつかなかったんだ、ぜんぜん」
「そのほうが良かったわ」
「プロのどろぼうだって、じいちゃんが言ってた」
「そうかね」
お母ちゃんは怖い顔をしていた。どろぼうに腹を立てているのかと思った。
「これからお母ちゃんの言うとおりにして」
「なにを?」
「このカバンに大事なものだけ入れて」
「だれの?」
「自分の。それとランドセルには教科書を全部入れて。連絡帳も忘れないで」
なんだかわけがわからなかったけど、言われたとおりにした。
ランドセルに入りきらなかった教科書を入れたら、カバンはほとんどいっぱいになった。
おもちゃ箱の中から今お気に入りのものだけを選ぶしかなかった。
ウルトラマンと仮面ライダーの人形とミニカーとビー玉を入れた。
しばらくするとハイヤーのクラクションがプップーと聞こえた。
お母ちゃんはいくつかのカバンを持って降りていった。
「もういい?いくわよ」
とって返してくるなり、そう促されたので、何か抜かりはないかと寝床のまわりだけは見ようと思った。
すると敷布団とベッドの枠の隙間に笛の付いた薄荷パイプが挟まっているのを見つけた。
もちろん中身はなくなっていて、吸ってもほのかにミントの匂いがするだけだった。
パイプの先にはリボンの騎士にでてくる妖精の顔が付いていたので、
タラリラッタリッタラッタと笛を吹こうとしたけど、ハーモニカも吹けないぼくにできるはずがない。
始末に困ったので妹にあげようと思い、パイプのひもを首にかけてやった。
ぽつんぽつんと階段を降りる妹のあとをお母ちゃんがぼくのカバンを持ってゆっくり続いた。
ぼくもしかたなく、ランドセルをひきずるようにして、階段を降りた。
一段踏み下るたびに片手に提げたランドセルのフタの金具が、ガチンガチンと鉄の階段にぶつかった。
ブースカの自転車持って行きたいなぁ、
サンダーバードは後で取りに来たいなぁ、
と自分の大事なもののことばかりぼんやり考えながらハイヤーに乗ってしまった。
ドアがバタンと閉まったとき、はっと大変なことに気がついた。
マサヒロ、ヒロシ、タケシ、ナオシ、それから、ふみちゃん。
みんなに何も言ってない。また会えるのかどうかも知らないのに。
しいちゃん、まっちゃん、お父ちゃん、ばあちゃん、それから、じいちゃん。
みんな何も言ってくれなかった。いつ帰ってきたらいいの。
後ろの座席の右側の窓の外を見ると、岡林商店が目の前にあった。
いつものように店の扉は開け放されていたけど、いつものようにおばあちゃんの姿は見えなかった。
発進した。車が一台やっと通れる幅の路地なので、とってもゆっくりと動いていく。
ふみちゃんちの方に目をやったけど、偶然誰かが出てくるような気配はなかった。
刈谷バアの家の前も通り過ぎた。
鶏小屋のある裏庭の前も同時に通り過ぎた。
そんなつもりはないのに、誰にも会うことなく誰にも声かけることもなくて、ぼくはしょんぼりした。
そのほかに言いようがない気持ちだった。
となりでは妹が、小さな小さな音を立てて、空っぽの薄荷パイプを吸っていた。
そしてぼくの幼少期は終わったのだった。
おしまい
その日はあっけなくやってきた。
学校から帰ってきて二階へかけあがり、靴脱ぎ場からランドセルを
部屋の中に放り込もうとしたら、お母ちゃんがいるのに気がついた。
「あれっ?おかえり」
「ただいま」
ぼくはじいちゃん子だったので、お母ちゃんに飛びつきはしなかった。
どうしていなくなったのか、聞いてみることすらしなかった。
何もなかったんだと思い込もうとしたのかもしれない。
そうであってほしいという願いのような気持ちはあったと思う。
だったら最近のことはすべてなかったことにすればいいのに、
ぼくの口は勝手に開いていた。
「この間、どろぼうがはいったんだよ」
「あら、そう」
「壁とね、レジを壊してね、お金を盗んでいったんだよ」
「それはこわかったねぇ」
「ううん、だれもね、気がつかなかったんだ、ぜんぜん」
「そのほうが良かったわ」
「プロのどろぼうだって、じいちゃんが言ってた」
「そうかね」
お母ちゃんは怖い顔をしていた。どろぼうに腹を立てているのかと思った。
「これからお母ちゃんの言うとおりにして」
「なにを?」
「このカバンに大事なものだけ入れて」
「だれの?」
「自分の。それとランドセルには教科書を全部入れて。連絡帳も忘れないで」
なんだかわけがわからなかったけど、言われたとおりにした。
ランドセルに入りきらなかった教科書を入れたら、カバンはほとんどいっぱいになった。
おもちゃ箱の中から今お気に入りのものだけを選ぶしかなかった。
ウルトラマンと仮面ライダーの人形とミニカーとビー玉を入れた。
しばらくするとハイヤーのクラクションがプップーと聞こえた。
お母ちゃんはいくつかのカバンを持って降りていった。
「もういい?いくわよ」
とって返してくるなり、そう促されたので、何か抜かりはないかと寝床のまわりだけは見ようと思った。
すると敷布団とベッドの枠の隙間に笛の付いた薄荷パイプが挟まっているのを見つけた。
もちろん中身はなくなっていて、吸ってもほのかにミントの匂いがするだけだった。
パイプの先にはリボンの騎士にでてくる妖精の顔が付いていたので、
タラリラッタリッタラッタと笛を吹こうとしたけど、ハーモニカも吹けないぼくにできるはずがない。
始末に困ったので妹にあげようと思い、パイプのひもを首にかけてやった。
ぽつんぽつんと階段を降りる妹のあとをお母ちゃんがぼくのカバンを持ってゆっくり続いた。
ぼくもしかたなく、ランドセルをひきずるようにして、階段を降りた。
一段踏み下るたびに片手に提げたランドセルのフタの金具が、ガチンガチンと鉄の階段にぶつかった。
ブースカの自転車持って行きたいなぁ、
サンダーバードは後で取りに来たいなぁ、
と自分の大事なもののことばかりぼんやり考えながらハイヤーに乗ってしまった。
ドアがバタンと閉まったとき、はっと大変なことに気がついた。
マサヒロ、ヒロシ、タケシ、ナオシ、それから、ふみちゃん。
みんなに何も言ってない。また会えるのかどうかも知らないのに。
しいちゃん、まっちゃん、お父ちゃん、ばあちゃん、それから、じいちゃん。
みんな何も言ってくれなかった。いつ帰ってきたらいいの。
後ろの座席の右側の窓の外を見ると、岡林商店が目の前にあった。
いつものように店の扉は開け放されていたけど、いつものようにおばあちゃんの姿は見えなかった。
発進した。車が一台やっと通れる幅の路地なので、とってもゆっくりと動いていく。
ふみちゃんちの方に目をやったけど、偶然誰かが出てくるような気配はなかった。
刈谷バアの家の前も通り過ぎた。
鶏小屋のある裏庭の前も同時に通り過ぎた。
そんなつもりはないのに、誰にも会うことなく誰にも声かけることもなくて、ぼくはしょんぼりした。
そのほかに言いようがない気持ちだった。
となりでは妹が、小さな小さな音を立てて、空っぽの薄荷パイプを吸っていた。
そしてぼくの幼少期は終わったのだった。
おしまい
宝永町248番地 第72話 [Wessay]
板壁と前歯
朝起きてみると何やら家じゅうがざわざわしている。
犬のレイの鳴き声もいつもと違って、
ただ散歩に連れて行けという吠え方じゃないような気もした。
「ばあちゃん、どうしたの?」
「どろぼうに入られた」
「え、いつ?どこから?」
「ゆうべじゃ、便所のところからじゃ」
母屋のはじっこにある便所まで行ってみた。
すると、男用の便器がふたつ並んでいるところの壁が破れていた。
壁といっても薄っぺらい板一枚で、その向こうはミカン水屋側の路地だ。
泥棒は路地から便所の板壁をこわして入ってきたのだ。
便器のすぐ脇が大きく開いているから、これではおしっこがしづらい。
探偵のような気分になって、ぼくは目がしゃきんと覚めてきた。
店の方に行ってみると、レジの周りに人が集まっていた。
おまわりさんとお父ちゃんが話をしていた。
「たぶん、バールでこじ開けたようだな」
「そんなもんないけどなあ」
「自分で用意してきてそのまま持ってったんだろう。他に被害は?」
「いや、レジの金だけみたいや」
バールというものは何だかわからないけど、レジの引き出しが、
いびつになって飛び出していることからすると、とっても固い道具なのだろう。
便所の壁もそれで引っぺがしたんだなと俄か探偵は判定した。
「それにしても誰にも気付かれずにこんなに荒っぽくできるもんなんだ」
と半ば感心しているのを見抜かれたわけじゃないと思うけど、じいちゃんが
「こりゃあ、プロの仕業かもしれんな」
とつぶやいた。
ぼくは「泥棒にもプロがいるんだ」と更に呑気に犯人の姿を想像していた。
でも間もなく「早くごはん食べて学校に行きなさい」という、ばあちゃんの一言で
ぼくの探偵ごっこは終わった。
ランドセルをしょって家を出るときにはもうおまわりさんの姿も見えなかった。
小学校からの帰り道、ドブを越えようとジャンプした拍子にぐらぐらしていた前歯が抜けた。
びっくりして飲み込みそうだったけど、運良く舌の上にとどまっていたので、
それを片手に握り締め、風通しのよくなった口をわざと半開きにして早足に帰った。
飛び込んでくる冷たい空気のつぶは、味はないけどおいしかった。
上の歯は縁の下のネズミにかじってもらい、下の歯は天井のネズミにかじってもらうと、
次に出てくる歯が丈夫になるんだとちょっと前にじいちゃんに教わった。
上の歯だったのでぼくは縁の下に投げ込んだ。
下の歯が抜けたときは天井裏ではなくて屋根の上に放り投げた。
瓦にぶつかってカチカチと小さな音がすることもあり、なぜかまったく音がしないこともあった。
屋根の上にネズミはいないだろうから、スズメが食べちゃうのかなと思った。
ところで店はいつものようにやっていた。
みんな何もなかったみたいに忙しく働いていた。
勘定場の壊されたレジは影も形もなく、代わりに菓子箱と小銭用に枡がいくつか並んでいた。
ぼくの前歯みたいにスースーしていた便所の壁は、
外からベニヤ板か何かを打ち付けて急場しのぎとしていた。
その修理されたところは、修理されたがゆえに異様な感じがあふれていて、
あらためてどろぼうの怖さがじわりとしみてきた。
そして次の日、店には新しいレジと、仏壇より大きな金庫が運ばれてきた。
朝起きてみると何やら家じゅうがざわざわしている。
犬のレイの鳴き声もいつもと違って、
ただ散歩に連れて行けという吠え方じゃないような気もした。
「ばあちゃん、どうしたの?」
「どろぼうに入られた」
「え、いつ?どこから?」
「ゆうべじゃ、便所のところからじゃ」
母屋のはじっこにある便所まで行ってみた。
すると、男用の便器がふたつ並んでいるところの壁が破れていた。
壁といっても薄っぺらい板一枚で、その向こうはミカン水屋側の路地だ。
泥棒は路地から便所の板壁をこわして入ってきたのだ。
便器のすぐ脇が大きく開いているから、これではおしっこがしづらい。
探偵のような気分になって、ぼくは目がしゃきんと覚めてきた。
店の方に行ってみると、レジの周りに人が集まっていた。
おまわりさんとお父ちゃんが話をしていた。
「たぶん、バールでこじ開けたようだな」
「そんなもんないけどなあ」
「自分で用意してきてそのまま持ってったんだろう。他に被害は?」
「いや、レジの金だけみたいや」
バールというものは何だかわからないけど、レジの引き出しが、
いびつになって飛び出していることからすると、とっても固い道具なのだろう。
便所の壁もそれで引っぺがしたんだなと俄か探偵は判定した。
「それにしても誰にも気付かれずにこんなに荒っぽくできるもんなんだ」
と半ば感心しているのを見抜かれたわけじゃないと思うけど、じいちゃんが
「こりゃあ、プロの仕業かもしれんな」
とつぶやいた。
ぼくは「泥棒にもプロがいるんだ」と更に呑気に犯人の姿を想像していた。
でも間もなく「早くごはん食べて学校に行きなさい」という、ばあちゃんの一言で
ぼくの探偵ごっこは終わった。
ランドセルをしょって家を出るときにはもうおまわりさんの姿も見えなかった。
小学校からの帰り道、ドブを越えようとジャンプした拍子にぐらぐらしていた前歯が抜けた。
びっくりして飲み込みそうだったけど、運良く舌の上にとどまっていたので、
それを片手に握り締め、風通しのよくなった口をわざと半開きにして早足に帰った。
飛び込んでくる冷たい空気のつぶは、味はないけどおいしかった。
上の歯は縁の下のネズミにかじってもらい、下の歯は天井のネズミにかじってもらうと、
次に出てくる歯が丈夫になるんだとちょっと前にじいちゃんに教わった。
上の歯だったのでぼくは縁の下に投げ込んだ。
下の歯が抜けたときは天井裏ではなくて屋根の上に放り投げた。
瓦にぶつかってカチカチと小さな音がすることもあり、なぜかまったく音がしないこともあった。
屋根の上にネズミはいないだろうから、スズメが食べちゃうのかなと思った。
ところで店はいつものようにやっていた。
みんな何もなかったみたいに忙しく働いていた。
勘定場の壊されたレジは影も形もなく、代わりに菓子箱と小銭用に枡がいくつか並んでいた。
ぼくの前歯みたいにスースーしていた便所の壁は、
外からベニヤ板か何かを打ち付けて急場しのぎとしていた。
その修理されたところは、修理されたがゆえに異様な感じがあふれていて、
あらためてどろぼうの怖さがじわりとしみてきた。
そして次の日、店には新しいレジと、仏壇より大きな金庫が運ばれてきた。
宝永町248番地 第71話 [Wessay]
肉桂と穴
ぼくは滅多に放課後に小学校の校庭で遊ばない。
いつもの遊び友だちのふみちゃんやマサヒロたちが別の小学校に通っているからでもある。
帰りに森のおじちゃんちに遊びに行ったり、フラフラと宛もなく寄り道するのが好きだからでもある。
でもタケシや同じ組の友だちとビー玉をするときは別だ。
校庭の隅にある鉄棒と植え込みの間の平らで地面の固い場所を競技場に選んでいる。
ほんとはビー玉を学校に持ってきてはいけないので、目立たない場所にしないとだめなのだ。
もちろん、ビー玉を賭けてやっているなんてことも内緒だ。
ぼくたちは「天地」という遊び方しか知らなかった。
お茶碗くらいの大きさの穴をサイコロの五の目のように五つ掘って遊ぶ。
順番に穴を辿って、一番先に一周したひとがオニになる。
オニになると他の人のビー玉に自分の玉を当てる。当てられた瞬間にその玉はオニの戦利品となる。
だから鬼ごっこやかくれんぼと違って、皆オニになることを目指す。
オニになれずにいると自分のビー玉はじわじわと減っていくだけだから。
オニになると自分のビー玉を選手交代させた。
とられてもいいやつからお気に入りの強い玉に変えるのだ。
大抵それは”スイギン”と呼ばれる、手に入りにくくて無色透明に近い、きれいなビー玉だった。
タケシがオニになった。
「よっしゃあ、オレがオニじゃあ、スイギンにするぞ」
「ええよ、はやくやれ」
「ほんなら、いくぞ」
「ガチーン」
ぼくの玉は当てられた。でもタケシの玉も勢いあまって植え込みの中まで転がった。
「アウトだ、アウト」
「ありゃあ、まいったぁ」
予め決めておいた範囲から外に出ると罰則となり、どこかの穴に入って一回休みとなる。
タケシがアウトになったからぼくのはとられなかった。
それどころか、次の番にぼくもオニになって、とうとうタケシのはまっている穴まで辿りついた。
「よっしゃあ、芋堀りじゃあ、覚悟せーよ」
芋堀りとは同じ穴の中にある相手の玉を穴の外に弾き出すことだ。
「カチーン」
うまくタケシの玉を穴から弾き出し、自分の玉は穴の中にとどまった。
「スイギンもらったー」
「くそー、やられたー」
ビー玉にあきるとぼくたちは西門の脇にある一本の木に集まった。
誰が言ったのかはわからないけど、この木は「ニッケイ」という木なのだそうだ。
ニッケイはいい香りのするめずらしい木らしいので、言いふらしてはいけないことになっていた。
その木に集まって何をするかというと、穴を掘るのだった。
これも誰が言ったのかわからないけど、ニッケイは根っこに値打ちがあるというのだ。
しかも先っちょの方のストローくらいの太さの根に限るらしい。
根を傷つけてはいけないので、最初は竹の切れ端や棒を使うけど、あとは手だ。
だからぼくたちは根っこが伸びてそうな場所を少し掘ってみて、
太い根があればそのままその周りを掘り下げていく。
そんなに深くは掘らないけど、手首まで入るくらいまでいく頃にはすっかり夕方だ。
だけど誰も帰らずにそれぞれの場所で堀り続けている。
だんだん根が細くなる方へと、途中で千切れないように手繰っていって、ようやく薄茶色のストローに辿りつく。
ブチッと折って土を払い落とした。
それからその根を鼻の近くに持っていって、なぞるように匂いをかいでみたけど、
全然いい香りなんかしなかった。
湿った赤土と枯れ葉がまざったような、雑巾がけしたての木の廊下のような臭いがするだけだった。
「なんだこれ、くさいよ」
「それがニッケイのにおいじゃないの」
「えー、そうかなぁ」
「そうだよ、たぶん」
誰も結論を出すことはできなかったけど、がっかりしていない子はいなかった。
その木は肉桂でもなんでもなかったのだ。
次の日、誰かが走っていて穴に足をとられて転んでしまった。
そしてすぐに”穴堀り禁止”が学校中に言い渡された。

ぼくは滅多に放課後に小学校の校庭で遊ばない。
いつもの遊び友だちのふみちゃんやマサヒロたちが別の小学校に通っているからでもある。
帰りに森のおじちゃんちに遊びに行ったり、フラフラと宛もなく寄り道するのが好きだからでもある。
でもタケシや同じ組の友だちとビー玉をするときは別だ。
校庭の隅にある鉄棒と植え込みの間の平らで地面の固い場所を競技場に選んでいる。
ほんとはビー玉を学校に持ってきてはいけないので、目立たない場所にしないとだめなのだ。
もちろん、ビー玉を賭けてやっているなんてことも内緒だ。
ぼくたちは「天地」という遊び方しか知らなかった。
お茶碗くらいの大きさの穴をサイコロの五の目のように五つ掘って遊ぶ。
順番に穴を辿って、一番先に一周したひとがオニになる。
オニになると他の人のビー玉に自分の玉を当てる。当てられた瞬間にその玉はオニの戦利品となる。
だから鬼ごっこやかくれんぼと違って、皆オニになることを目指す。
オニになれずにいると自分のビー玉はじわじわと減っていくだけだから。
オニになると自分のビー玉を選手交代させた。
とられてもいいやつからお気に入りの強い玉に変えるのだ。
大抵それは”スイギン”と呼ばれる、手に入りにくくて無色透明に近い、きれいなビー玉だった。
タケシがオニになった。
「よっしゃあ、オレがオニじゃあ、スイギンにするぞ」
「ええよ、はやくやれ」
「ほんなら、いくぞ」
「ガチーン」
ぼくの玉は当てられた。でもタケシの玉も勢いあまって植え込みの中まで転がった。
「アウトだ、アウト」
「ありゃあ、まいったぁ」
予め決めておいた範囲から外に出ると罰則となり、どこかの穴に入って一回休みとなる。
タケシがアウトになったからぼくのはとられなかった。
それどころか、次の番にぼくもオニになって、とうとうタケシのはまっている穴まで辿りついた。
「よっしゃあ、芋堀りじゃあ、覚悟せーよ」
芋堀りとは同じ穴の中にある相手の玉を穴の外に弾き出すことだ。
「カチーン」
うまくタケシの玉を穴から弾き出し、自分の玉は穴の中にとどまった。
「スイギンもらったー」
「くそー、やられたー」
ビー玉にあきるとぼくたちは西門の脇にある一本の木に集まった。
誰が言ったのかはわからないけど、この木は「ニッケイ」という木なのだそうだ。
ニッケイはいい香りのするめずらしい木らしいので、言いふらしてはいけないことになっていた。
その木に集まって何をするかというと、穴を掘るのだった。
これも誰が言ったのかわからないけど、ニッケイは根っこに値打ちがあるというのだ。
しかも先っちょの方のストローくらいの太さの根に限るらしい。
根を傷つけてはいけないので、最初は竹の切れ端や棒を使うけど、あとは手だ。
だからぼくたちは根っこが伸びてそうな場所を少し掘ってみて、
太い根があればそのままその周りを掘り下げていく。
そんなに深くは掘らないけど、手首まで入るくらいまでいく頃にはすっかり夕方だ。
だけど誰も帰らずにそれぞれの場所で堀り続けている。
だんだん根が細くなる方へと、途中で千切れないように手繰っていって、ようやく薄茶色のストローに辿りつく。
ブチッと折って土を払い落とした。
それからその根を鼻の近くに持っていって、なぞるように匂いをかいでみたけど、
全然いい香りなんかしなかった。
湿った赤土と枯れ葉がまざったような、雑巾がけしたての木の廊下のような臭いがするだけだった。
「なんだこれ、くさいよ」
「それがニッケイのにおいじゃないの」
「えー、そうかなぁ」
「そうだよ、たぶん」
誰も結論を出すことはできなかったけど、がっかりしていない子はいなかった。
その木は肉桂でもなんでもなかったのだ。
次の日、誰かが走っていて穴に足をとられて転んでしまった。
そしてすぐに”穴堀り禁止”が学校中に言い渡された。
宝永町248番地 第70話 [Wessay]
三輪車
ぼくは長ズボンを持ってない。
幼稚園のお遊戯会以来、タイツも履いたことがない。
冬になっても平気で半ズボンで走り回っている。
お母ちゃんが出て行って幾日かたって、太ももが吹く風で白くなりはじめた頃、
お父ちゃんやじいちゃんに「いつ帰ってくるの」と聞いた。
だけど誰も答えてくれなかった。
かといって大騒ぎしている様子ではない。
皆ちょっと困ったような顔をしているけど、誰も探しに行きはしない。
じゃあやっぱり家出じゃないのかなとも思ったけど、
どこかにでかけているだけなら、いつ帰ってくるかはわかるはずだ。
・・・
結局ぼくにはわからなかった。
だけど「家出したの?」と誰かに確かめることもできなかった。
聞いてはいけないという気がしたから、ぼくはただ黙っていた。
その内に帰ってくるだろうと信じることが簡単にできるくらい、
ぼくはまだ幼かった。
今日は気まぐれを起こして三輪車をひっぱり出してきて、いつもの神社に遊びに行った。
三輪車はもう小さくなっていて、こぎづらかったけど、それがおもしろかった。
地面がでこぼこしているところだとバランスがとれずにグラグラしてしまう。
ひとりで遊んでいると見かけない子が数人、境内にやってきた。
目が合ったけどお互い声はかけなかった。同じ小学校の子かどうかも定かではない。
しばらく彼らは境内の上の段で遊んでいたが、遊びの種目を変えたのか、
ぼくがふらふらと三輪車をこいでいる下の段に降りてきた。
「オレたち、ここで遊ぶから、おまえよそへ行ってくれ」
「いやだ、ぼくが先に遊んでたんだ、おまえらが行け」
「ここで三輪車乗らなくてもいいだろ」
「ここがいいんだ!」
周りを取り囲まれていた。
寄ってたかって無茶苦茶な非難を浴びせられ、無理やり三輪車を奪われた。
「返せ」
「返さん」
「先生に言うぞ」
「言えるものなら言え」
言われてみると彼らの先生が誰かなんて知らないから言えない。
そう思った瞬間にひとりが三輪車を放り出した。
ぼくは横倒しになった三輪車の片方のハンドルを持って引きずりながら境内を後にした。
参道まできて、三輪車にまたがりなおして家に向かった。
くやしくて涙が出た。
まるでペダルがポンプになってしまったかのように、踏むたびに涙がにじみ出た。
ぼくの家は参道入り口のまん前にある。
ちょうどお父ちゃんが店頭に立っていた。ひょっとしたら見られていたかもしれない。
「どうした」
「なんでもない」
「何で泣いてるんだ」
「けんかした」
「ばかたれ、けんかしても泣いて帰ってくるんじゃない」
そう言い放った瞬間、お父ちゃんはぼくの太ももをひっぱたいた。
「バチーン」
みるみるぼくの足には大きな赤い手形が浮き上がってきた。
ものすごく痛かったけど何故か涙は止まってしまっていた。
「ほら、もういっぺん行って来い」
「うん」
ぼくは三輪車を店先に置き去りにして、境内へと引き返した。
どういうわけか、やつらはまた上の段で遊んでいた。
「おーい」
「なんだ」
「ぼくもまぜてくれ」
「んー、わかった、いいよ」
腹の虫が収まったわけではなかったけど、やっつけてやろうという気はおきなかった。
へなちょこかもしれないけど、対等に遊べればそれでよかった。
そしてぼくはお母ちゃんもそのうちに帰ってくるだろうと自分のことと重ねてしまった。

ぼくは長ズボンを持ってない。
幼稚園のお遊戯会以来、タイツも履いたことがない。
冬になっても平気で半ズボンで走り回っている。
お母ちゃんが出て行って幾日かたって、太ももが吹く風で白くなりはじめた頃、
お父ちゃんやじいちゃんに「いつ帰ってくるの」と聞いた。
だけど誰も答えてくれなかった。
かといって大騒ぎしている様子ではない。
皆ちょっと困ったような顔をしているけど、誰も探しに行きはしない。
じゃあやっぱり家出じゃないのかなとも思ったけど、
どこかにでかけているだけなら、いつ帰ってくるかはわかるはずだ。
・・・
結局ぼくにはわからなかった。
だけど「家出したの?」と誰かに確かめることもできなかった。
聞いてはいけないという気がしたから、ぼくはただ黙っていた。
その内に帰ってくるだろうと信じることが簡単にできるくらい、
ぼくはまだ幼かった。
今日は気まぐれを起こして三輪車をひっぱり出してきて、いつもの神社に遊びに行った。
三輪車はもう小さくなっていて、こぎづらかったけど、それがおもしろかった。
地面がでこぼこしているところだとバランスがとれずにグラグラしてしまう。
ひとりで遊んでいると見かけない子が数人、境内にやってきた。
目が合ったけどお互い声はかけなかった。同じ小学校の子かどうかも定かではない。
しばらく彼らは境内の上の段で遊んでいたが、遊びの種目を変えたのか、
ぼくがふらふらと三輪車をこいでいる下の段に降りてきた。
「オレたち、ここで遊ぶから、おまえよそへ行ってくれ」
「いやだ、ぼくが先に遊んでたんだ、おまえらが行け」
「ここで三輪車乗らなくてもいいだろ」
「ここがいいんだ!」
周りを取り囲まれていた。
寄ってたかって無茶苦茶な非難を浴びせられ、無理やり三輪車を奪われた。
「返せ」
「返さん」
「先生に言うぞ」
「言えるものなら言え」
言われてみると彼らの先生が誰かなんて知らないから言えない。
そう思った瞬間にひとりが三輪車を放り出した。
ぼくは横倒しになった三輪車の片方のハンドルを持って引きずりながら境内を後にした。
参道まできて、三輪車にまたがりなおして家に向かった。
くやしくて涙が出た。
まるでペダルがポンプになってしまったかのように、踏むたびに涙がにじみ出た。
ぼくの家は参道入り口のまん前にある。
ちょうどお父ちゃんが店頭に立っていた。ひょっとしたら見られていたかもしれない。
「どうした」
「なんでもない」
「何で泣いてるんだ」
「けんかした」
「ばかたれ、けんかしても泣いて帰ってくるんじゃない」
そう言い放った瞬間、お父ちゃんはぼくの太ももをひっぱたいた。
「バチーン」
みるみるぼくの足には大きな赤い手形が浮き上がってきた。
ものすごく痛かったけど何故か涙は止まってしまっていた。
「ほら、もういっぺん行って来い」
「うん」
ぼくは三輪車を店先に置き去りにして、境内へと引き返した。
どういうわけか、やつらはまた上の段で遊んでいた。
「おーい」
「なんだ」
「ぼくもまぜてくれ」
「んー、わかった、いいよ」
腹の虫が収まったわけではなかったけど、やっつけてやろうという気はおきなかった。
へなちょこかもしれないけど、対等に遊べればそれでよかった。
そしてぼくはお母ちゃんもそのうちに帰ってくるだろうと自分のことと重ねてしまった。

宝永町248番地 第69話 [Wessay]
毛布
お母ちゃんはよく刺繍をする。
白い布に色のついた糸を縫いこんでいく。
ひと針ふた針ではわからないけれど、だんだんと形ができていく。
緑色の糸は葉っぱになり、緋色の糸は花びらになり、黄土色の糸は蔓になる。
何度見ても何かの形になる瞬間はまるで手品のようだ。
でもタネはない。やさしく細やかな作業が織りなしただけだ。
ぼくのお気に入りの薄い綿毛布の端にも小さな蝶の刺繍がしてあった。
葉っぱは綻びかけていたけれど、きっと春が来るまで毎日それに包まるだろう。
うとうとしながら掛け布の端をなぞるのがぼくの癖でもあった。
昨夜は暑くて寝苦しかったけど毛布を離したくなかったから、寝間着をぜんぶ脱いだ。
裸で毛布の端をもてあそびながら気持ちよくうとうとしていたら、
いつもはそんなことないのに、お父ちゃんとお母ちゃんが様子を見にきた。
「なんでまた、こいつは裸で」
「汗に浮いてるわね」
二段ベッドの上の床は丁度大人の目の高さにあるので、ふたりの声が耳元で聴こえる。
「だって暑いんだもの・・」
声になったかどうかはわからない。ぼくは夢うつつの中で無意識にこたえていた。
でも同時にとってもはずかしかった。自分が赤ん坊のように思われるのが嫌だったのだ。
毛布を掛けなおして、ふたりが子ども部屋から出て行く前にぼくはもう眠りに落ちていた。
それからもう少し寒くなって、毛布の中にすっぽり入っても汗をかかなくなった頃の夜、
お父ちゃんのお友だちのお客さんがやってきた。
お母ちゃんが刺繍をする場所でもある、台所と居間がいっしょになっている部屋で、
酒盛りがはじまった。いつもの”お客”といわれる宴会じゃない。
「おい、ビール取ってきてくれ」
「何本?」
「五本」
「五本なんて無理よ」
お母ちゃんが二本にしてくれたので、ぼくは店の冷蔵庫にビールを取りにいった。
もう閉店した店は真っ暗だったので、入り口の柱のスイッチをパチンと押した。
チカチカッという音とともにレジの上の蛍光灯が点いた。
それだけでは暗かったけど、冷蔵庫の前まで行って下の観音開きのドアを開けた。
中に入っている大瓶のビールケースをずりずりと引っ張って外まで出し、
ビールの大瓶を一本ずつ引き抜いて、全部で三本の瓶を床に立てた。
ケースを冷蔵庫の中に持ち上げ、押し込んで、銀色の金属のドアをどすっと閉じた。
ぼくはビール瓶の首のとこを右手と左手で一本ずつ握り、三本目を両手の指先で挟んだ。
それから店から奥に続く通路に出ようとして困った。
スイッチが押せない。
でも電灯はそのまま点けておくことにした。
多分また取りに来ると思ったから。
二階の部屋に戻ると、待ってましたとばかりにシュポシュポとビールの栓が抜かれた。
お父ちゃんはぼくのコップにもビールを注いだ。しかもなみなみと。
「かんぱーい」
「かんばーい」
ぼくは喉が渇いていたので、コップの半分くらい一気に飲んだ。
夕飯のときに時々ビールの泡だけ飲まされていたので何も躊躇しなかった。
お刺身やお寿司もおいしかった。
お腹もいっぱいになってくるとぼくは気持ちよくなってきた。
いつもはあんまりしないのに、お父ちゃんの背中にまわってまとわりついたり、
知らないおじさんに大きな声で質問したり、子ども部屋からおもちゃを持ってきて、
見せびらかしたり無理やり触らせたりと、自分でも制御不能になった。
終いには続き部屋になっているとなりの寝室のベッドの上に登って、
トランポリンをするようにジャンプしながら歌を唄ってしまったけど止められなかった。
ぼくは自分が酔っているとわかった。
わかったけどどうしようもなかった。
体が勝手に動いて、喉が勝手に声を出した。
「へんーしんっ!とぉっ!」
「ラ・イ・ダー・・・キーック!」
酔っ払いの子どもにビールを持って来いという大人はいなかったので、
ぼくはビールの運び係りからは放免された。
もっとも間もなくぼくはそのままベッドで気を失うように寝入ってしまったのだった。
目が覚めるとぼくは子ども部屋の二段ベッドの上の段にいた。
裸にはなってなくて寝間着をきてた。刺繍入りのくたくたの綿毛布をかぶって。
いつもの朝だった。鶏の世話をしなくては。
そしてまた平和な普段の日々が繰り返されると思っていたのに、突然お母ちゃんが家出した。

お母ちゃんはよく刺繍をする。
白い布に色のついた糸を縫いこんでいく。
ひと針ふた針ではわからないけれど、だんだんと形ができていく。
緑色の糸は葉っぱになり、緋色の糸は花びらになり、黄土色の糸は蔓になる。
何度見ても何かの形になる瞬間はまるで手品のようだ。
でもタネはない。やさしく細やかな作業が織りなしただけだ。
ぼくのお気に入りの薄い綿毛布の端にも小さな蝶の刺繍がしてあった。
葉っぱは綻びかけていたけれど、きっと春が来るまで毎日それに包まるだろう。
うとうとしながら掛け布の端をなぞるのがぼくの癖でもあった。
昨夜は暑くて寝苦しかったけど毛布を離したくなかったから、寝間着をぜんぶ脱いだ。
裸で毛布の端をもてあそびながら気持ちよくうとうとしていたら、
いつもはそんなことないのに、お父ちゃんとお母ちゃんが様子を見にきた。
「なんでまた、こいつは裸で」
「汗に浮いてるわね」
二段ベッドの上の床は丁度大人の目の高さにあるので、ふたりの声が耳元で聴こえる。
「だって暑いんだもの・・」
声になったかどうかはわからない。ぼくは夢うつつの中で無意識にこたえていた。
でも同時にとってもはずかしかった。自分が赤ん坊のように思われるのが嫌だったのだ。
毛布を掛けなおして、ふたりが子ども部屋から出て行く前にぼくはもう眠りに落ちていた。
それからもう少し寒くなって、毛布の中にすっぽり入っても汗をかかなくなった頃の夜、
お父ちゃんのお友だちのお客さんがやってきた。
お母ちゃんが刺繍をする場所でもある、台所と居間がいっしょになっている部屋で、
酒盛りがはじまった。いつもの”お客”といわれる宴会じゃない。
「おい、ビール取ってきてくれ」
「何本?」
「五本」
「五本なんて無理よ」
お母ちゃんが二本にしてくれたので、ぼくは店の冷蔵庫にビールを取りにいった。
もう閉店した店は真っ暗だったので、入り口の柱のスイッチをパチンと押した。
チカチカッという音とともにレジの上の蛍光灯が点いた。
それだけでは暗かったけど、冷蔵庫の前まで行って下の観音開きのドアを開けた。
中に入っている大瓶のビールケースをずりずりと引っ張って外まで出し、
ビールの大瓶を一本ずつ引き抜いて、全部で三本の瓶を床に立てた。
ケースを冷蔵庫の中に持ち上げ、押し込んで、銀色の金属のドアをどすっと閉じた。
ぼくはビール瓶の首のとこを右手と左手で一本ずつ握り、三本目を両手の指先で挟んだ。
それから店から奥に続く通路に出ようとして困った。
スイッチが押せない。
でも電灯はそのまま点けておくことにした。
多分また取りに来ると思ったから。
二階の部屋に戻ると、待ってましたとばかりにシュポシュポとビールの栓が抜かれた。
お父ちゃんはぼくのコップにもビールを注いだ。しかもなみなみと。
「かんぱーい」
「かんばーい」
ぼくは喉が渇いていたので、コップの半分くらい一気に飲んだ。
夕飯のときに時々ビールの泡だけ飲まされていたので何も躊躇しなかった。
お刺身やお寿司もおいしかった。
お腹もいっぱいになってくるとぼくは気持ちよくなってきた。
いつもはあんまりしないのに、お父ちゃんの背中にまわってまとわりついたり、
知らないおじさんに大きな声で質問したり、子ども部屋からおもちゃを持ってきて、
見せびらかしたり無理やり触らせたりと、自分でも制御不能になった。
終いには続き部屋になっているとなりの寝室のベッドの上に登って、
トランポリンをするようにジャンプしながら歌を唄ってしまったけど止められなかった。
ぼくは自分が酔っているとわかった。
わかったけどどうしようもなかった。
体が勝手に動いて、喉が勝手に声を出した。
「へんーしんっ!とぉっ!」
「ラ・イ・ダー・・・キーック!」
酔っ払いの子どもにビールを持って来いという大人はいなかったので、
ぼくはビールの運び係りからは放免された。
もっとも間もなくぼくはそのままベッドで気を失うように寝入ってしまったのだった。
目が覚めるとぼくは子ども部屋の二段ベッドの上の段にいた。
裸にはなってなくて寝間着をきてた。刺繍入りのくたくたの綿毛布をかぶって。
いつもの朝だった。鶏の世話をしなくては。
そしてまた平和な普段の日々が繰り返されると思っていたのに、突然お母ちゃんが家出した。
宝永町248番地 第68話 [Wessay]
白い飴と紅いお姫さま
ぼくは肉が嫌いだ。
ウシもブタもトリも全部だめだ。
ひき肉ならなんとか食べられるけど、ソーセージは魚の身のじゃないと食べられない。
給食でいつも出てくるクジラは残せないのでしょうがなく食べる。
コロッケは大好きだ。特に隣町の商店街のお肉屋さんのは飛び切りおいしい。
ばあちゃんもお母ちゃんもコロッケだけは隣町まで行って買ってくる。
今日のお昼のおかずがそれだった。
とにかく匂いが断然違う。香ばしくてちょっとだけ甘い。
それは肉でも野菜でもない、うっとりとするごちそうという名前の食べ物だ。
ひき肉はほんの少ししか入ってないけど、大人たちもみんな大好きみたいだった。
そんなぜいたくな日曜日のお昼を食べ終わるやいなや、すぐ着替えろと言われた。
みんなでどこかに行くらしい。
着替えはなぜか箱に入っていた。よそ行きの服だ。妹の箱もあった。
ぼくは背広みたいなものを着せられた。黒い靴もはいた。
妹は白と桃色のもこもこしたワンピースを着せられて、頭にリボンを付けられた。
「どこに行くの?」
「七五三」
「しちごちゃん?」
「し、ち、ご、さん」
「何それ?」
「五歳で行かなかったからね」
着いたところは「てんじんさん」という神社だった。
鳥居の前には露店もでていて、まるでお祭りみたいだ。
どこからか砂糖が焦げたような、揚げたてのコロッケに似たようないい匂いが漂ってくる。
大きな朱色の鳥居をくぐって参道をお父ちゃんとお母ちゃんと妹と歩いた。
同じようによそ行きの服や着物姿の大人や子どもが大勢いた。
みんなが玉砂利を踏むジャラジャラという音が境内に響き渡る。
ぼくもわざと靴をひこずって、盛大に音を立てて歩いた。
「こら、靴がよごれる、もっと静かに歩きなさい」
しょうがないから、手水舎で洗った手を半ズボンの裾で拭いてからは、
横断歩道の縦の線のように並べられている細長い石の上を境内の奥に向かって辿った。
こうすれば音はでないし、歩くのもちょっと楽しい。
もう甘い匂いがしなくなった参道をしばらく進むと、
本殿の前の広場にあがる数段の石段の上にこちらを向いて手を振る家族がいた。
お父ちゃんも手を振ってこたえ、お母ちゃんはお辞儀をした。
遠くからでもはっきりと目立つ、さざんかのような紅と白の着物の子は見覚えがあった。
ぼくの”イイナズケ”らしい、ちさちゃんに違いない。
ぼくは石の上を歩くのをやめた。
近づいて大人たちが挨拶している間、ぼくはズボンが濡れていないかどうか確かめていた。
ズボンはもう乾いていたけど、
おとなしくじっと立っている彼女にぼくは声をかけることができなかった。
ちさちゃんがぼくのことを覚えているのかどうか窺い知ることができなかった。
お参りが終わって、木でできた階段状の坂を下りながら、ぼくは振り仰いでみた。
そこには神殿の柱の朱色と重なり合って、花のようにみえる紅い袖の女の子がいた。
そのほころんだ顔がちょっと大人びてみえたけど、なぜかほっとした。
「ねぇねぇ、何か買って」
「今アメを買ってあげるから、ちょっと待ってなさい」
綿菓子かキャンディーを想像して待っていたぼくたちに渡されたのは、
奇妙に長細くて白い紙袋だった。
そう言えば、参道ですれ違う子どもが手に手にこれと同じものを提げていたかもしれない。
「何?これ」
「ちとせあめ」
「食べていい?」
「お家にかえってからね」
「えー」
参道を引き返す皆の一番後ろをぼくはわざとゆっくり従った。
アメを食べるためだ。
びっくりしたことに袋の中には長細いアメが一本しか入っていなかった。
それをひっぱり出してぼくは先っちょをペロペロと舐めながら歩いていると、
ちさちゃんが振り向いてくすりと笑った。
ぼくはあんまりおいしくないよという顔をしたつもりだったけど、
たぶんうまくは伝わらなかったと思う。
鳥居のところまで来たころには、アメの端は剣先のように細く尖った。
大人たちは何やら立ち止まって相談をはじめたので、
ぼくは退屈して千歳飴を刀のように振り回していたら、不意にポキリと折れて地面に落ちた。
格好つけようとしたバチが当たったのかもしれないと思った。
「あーあ」
「あーあーもう」
お母ちゃんが落ちた白い刀を拾って袋に入れてくれた。
「これもう食べたらだめよ」
「えー」
「わたしの半分あげようか?」
突然、イイナズケのお姫さまがやさしいことを言ってくれたので面食らってしまった。
「いらんいらん、あんまりおいしくないから」
「はははは、そう」
「はははは、うん」
「じゃあ、お父ちゃんはこれからおじさんと用事があるから」
「わしは一遍家に帰ってから行くから、先に行っててくれ」
「わかった」
どうやら、お父ちゃんたちはこれからどこかに行くらしい。
ちさちゃん家はすぐ近所のようだ。
ぼくは道路の向こう側へ渡るちさちゃんに手を振った。
夕焼けの赤い光に照らされて、振り向いたお姫さまの頬っぺたも袖の色と同じだった。
「バイバーイ」
「バイバーイ」
そしてぼくたちが再会するのは、このあと五年余りの月日が流れてからのことになる。
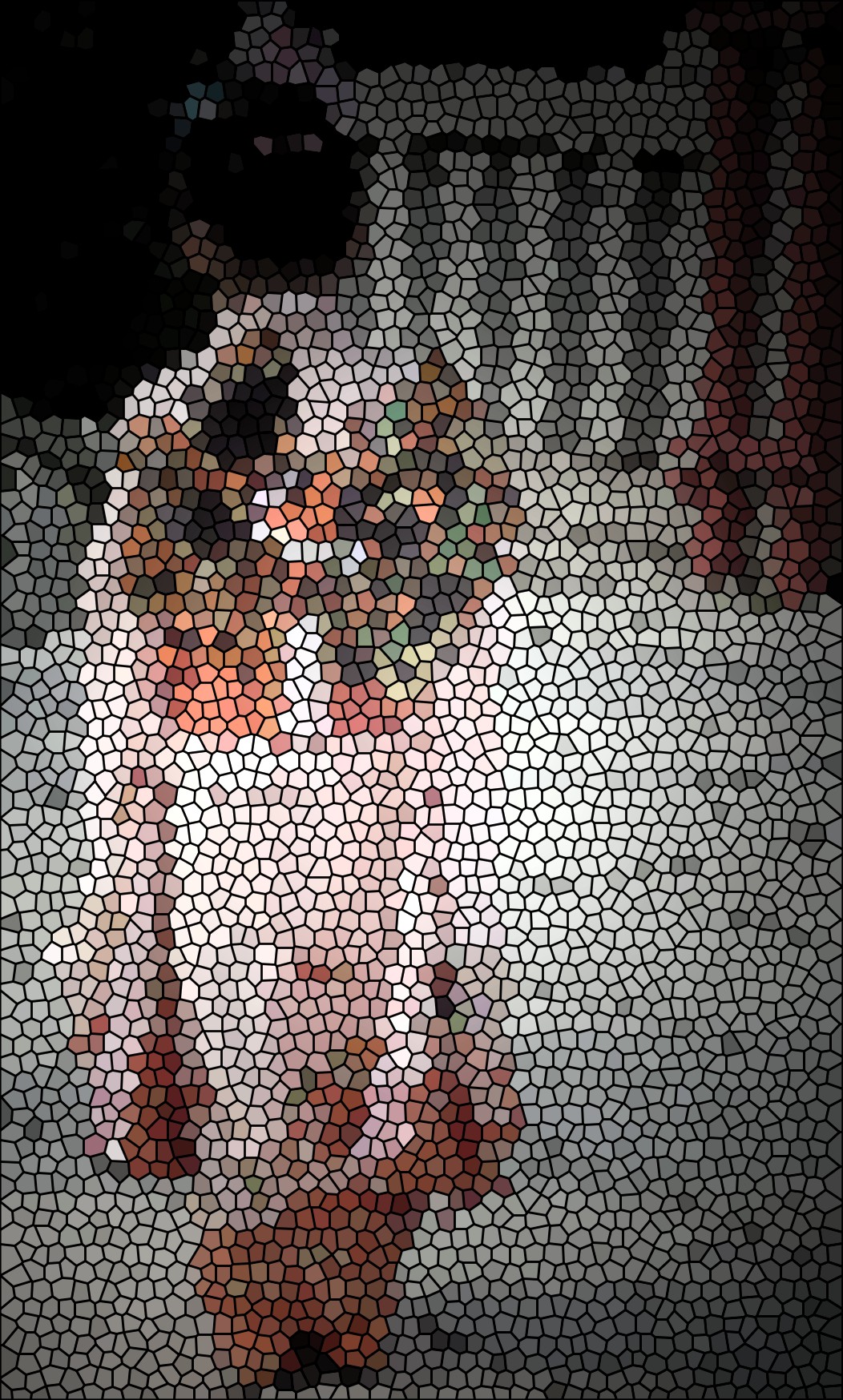
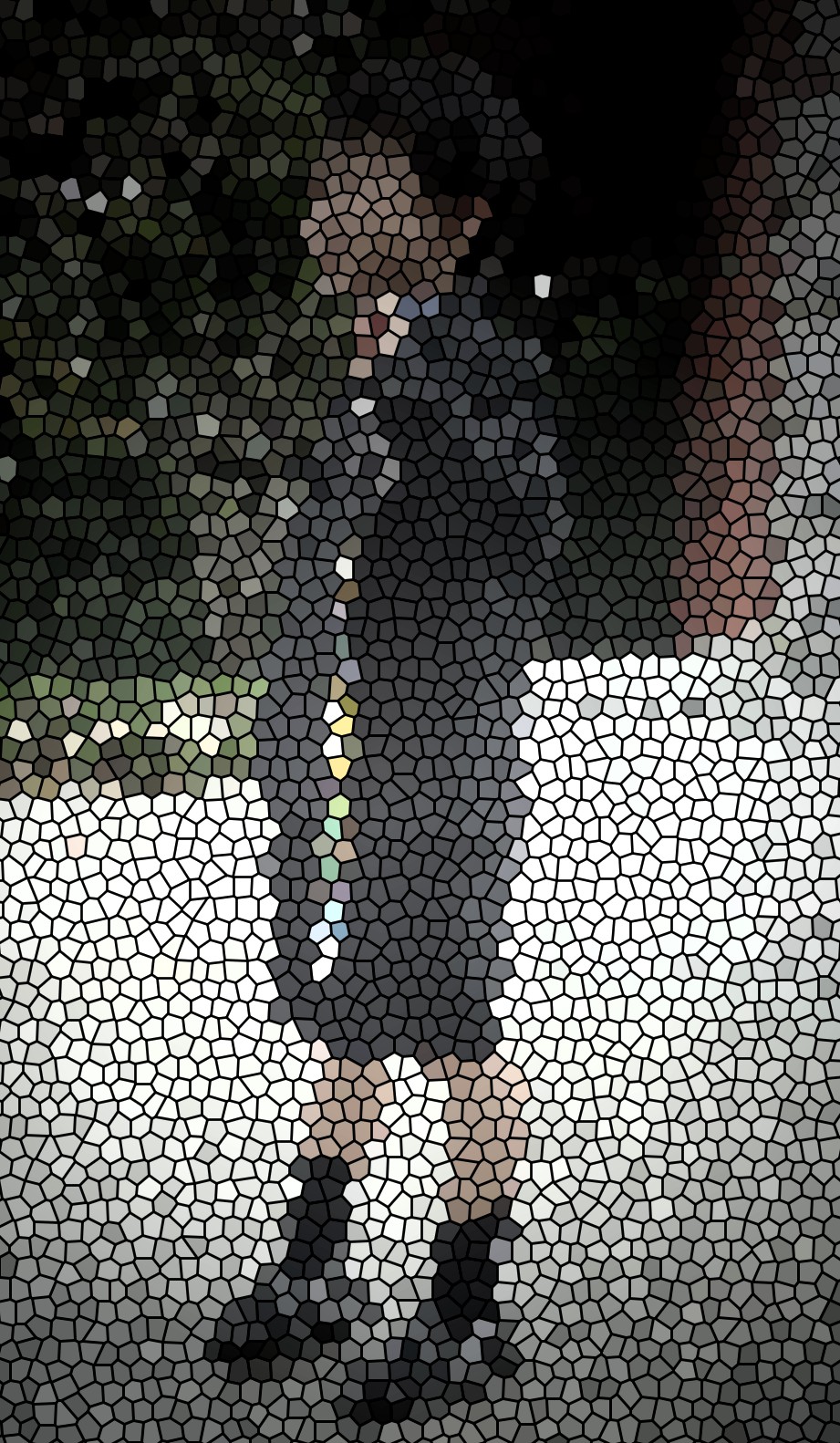
ぼくは肉が嫌いだ。
ウシもブタもトリも全部だめだ。
ひき肉ならなんとか食べられるけど、ソーセージは魚の身のじゃないと食べられない。
給食でいつも出てくるクジラは残せないのでしょうがなく食べる。
コロッケは大好きだ。特に隣町の商店街のお肉屋さんのは飛び切りおいしい。
ばあちゃんもお母ちゃんもコロッケだけは隣町まで行って買ってくる。
今日のお昼のおかずがそれだった。
とにかく匂いが断然違う。香ばしくてちょっとだけ甘い。
それは肉でも野菜でもない、うっとりとするごちそうという名前の食べ物だ。
ひき肉はほんの少ししか入ってないけど、大人たちもみんな大好きみたいだった。
そんなぜいたくな日曜日のお昼を食べ終わるやいなや、すぐ着替えろと言われた。
みんなでどこかに行くらしい。
着替えはなぜか箱に入っていた。よそ行きの服だ。妹の箱もあった。
ぼくは背広みたいなものを着せられた。黒い靴もはいた。
妹は白と桃色のもこもこしたワンピースを着せられて、頭にリボンを付けられた。
「どこに行くの?」
「七五三」
「しちごちゃん?」
「し、ち、ご、さん」
「何それ?」
「五歳で行かなかったからね」
着いたところは「てんじんさん」という神社だった。
鳥居の前には露店もでていて、まるでお祭りみたいだ。
どこからか砂糖が焦げたような、揚げたてのコロッケに似たようないい匂いが漂ってくる。
大きな朱色の鳥居をくぐって参道をお父ちゃんとお母ちゃんと妹と歩いた。
同じようによそ行きの服や着物姿の大人や子どもが大勢いた。
みんなが玉砂利を踏むジャラジャラという音が境内に響き渡る。
ぼくもわざと靴をひこずって、盛大に音を立てて歩いた。
「こら、靴がよごれる、もっと静かに歩きなさい」
しょうがないから、手水舎で洗った手を半ズボンの裾で拭いてからは、
横断歩道の縦の線のように並べられている細長い石の上を境内の奥に向かって辿った。
こうすれば音はでないし、歩くのもちょっと楽しい。
もう甘い匂いがしなくなった参道をしばらく進むと、
本殿の前の広場にあがる数段の石段の上にこちらを向いて手を振る家族がいた。
お父ちゃんも手を振ってこたえ、お母ちゃんはお辞儀をした。
遠くからでもはっきりと目立つ、さざんかのような紅と白の着物の子は見覚えがあった。
ぼくの”イイナズケ”らしい、ちさちゃんに違いない。
ぼくは石の上を歩くのをやめた。
近づいて大人たちが挨拶している間、ぼくはズボンが濡れていないかどうか確かめていた。
ズボンはもう乾いていたけど、
おとなしくじっと立っている彼女にぼくは声をかけることができなかった。
ちさちゃんがぼくのことを覚えているのかどうか窺い知ることができなかった。
お参りが終わって、木でできた階段状の坂を下りながら、ぼくは振り仰いでみた。
そこには神殿の柱の朱色と重なり合って、花のようにみえる紅い袖の女の子がいた。
そのほころんだ顔がちょっと大人びてみえたけど、なぜかほっとした。
「ねぇねぇ、何か買って」
「今アメを買ってあげるから、ちょっと待ってなさい」
綿菓子かキャンディーを想像して待っていたぼくたちに渡されたのは、
奇妙に長細くて白い紙袋だった。
そう言えば、参道ですれ違う子どもが手に手にこれと同じものを提げていたかもしれない。
「何?これ」
「ちとせあめ」
「食べていい?」
「お家にかえってからね」
「えー」
参道を引き返す皆の一番後ろをぼくはわざとゆっくり従った。
アメを食べるためだ。
びっくりしたことに袋の中には長細いアメが一本しか入っていなかった。
それをひっぱり出してぼくは先っちょをペロペロと舐めながら歩いていると、
ちさちゃんが振り向いてくすりと笑った。
ぼくはあんまりおいしくないよという顔をしたつもりだったけど、
たぶんうまくは伝わらなかったと思う。
鳥居のところまで来たころには、アメの端は剣先のように細く尖った。
大人たちは何やら立ち止まって相談をはじめたので、
ぼくは退屈して千歳飴を刀のように振り回していたら、不意にポキリと折れて地面に落ちた。
格好つけようとしたバチが当たったのかもしれないと思った。
「あーあ」
「あーあーもう」
お母ちゃんが落ちた白い刀を拾って袋に入れてくれた。
「これもう食べたらだめよ」
「えー」
「わたしの半分あげようか?」
突然、イイナズケのお姫さまがやさしいことを言ってくれたので面食らってしまった。
「いらんいらん、あんまりおいしくないから」
「はははは、そう」
「はははは、うん」
「じゃあ、お父ちゃんはこれからおじさんと用事があるから」
「わしは一遍家に帰ってから行くから、先に行っててくれ」
「わかった」
どうやら、お父ちゃんたちはこれからどこかに行くらしい。
ちさちゃん家はすぐ近所のようだ。
ぼくは道路の向こう側へ渡るちさちゃんに手を振った。
夕焼けの赤い光に照らされて、振り向いたお姫さまの頬っぺたも袖の色と同じだった。
「バイバーイ」
「バイバーイ」
そしてぼくたちが再会するのは、このあと五年余りの月日が流れてからのことになる。
宝永町248番地 第67話 [Wessay]
研ぎ屋
同じクラスにノリミチ君という子がいた。
まわりに太っている子はいないけど、その子は特に色が白くて痩せていた。
しかもおとなしくて動作も速くない。いや、とっても遅い。
みんなは「ノンちゃん」と呼んでいた。
ノンちゃんはどこか危なっかしくて、皆が気にかけてあげなくてはいけないような、
同級生なのに弟のような存在だった。
そんなノンちゃんとぼくはある日、突然接近することになった。
帰りの挨拶がおわって教室の出口に向かうぼくの視界に、ランドセルを背負おうとしている
ノンちゃんのゆっくりした動きが入ってきた。
一方の肩ベルトを腕に通して、もう一方に腕を通そうとして体をよじった瞬間、
ランドセルが傾いて、べろっと開いたフタの中から何かがボタッと床に落ちた。
学校には持ってきてはいけないオモチャ。塩ビというやわらかいプラスチックの人形。
それは仮面ライダーだった。
「あっ、これどうしたの?」
「家から持ってきた」
「持ってきたらだめだよ」
「でも持ってきた、持ってきただけ」
「早く隠しな」
「うん」
「ねぇ、他にも持ってるの?」
「うん、家にある」
「ねぇ、一緒に遊ぶ?」
「うん」
ぼくたちは連れ立って下校した。
家の方向が同じことがわかった。しかもノンちゃん家はぼくの通学路の途中にあった。
とぎ屋さんがある角から三軒目だった。
さっそく家にあがらせてもらって、ぼくは仮面ライダーの人形を見せてもらった。
怪人の人形も何体かあった。クモ男にカマキリ男。
無口なはずのノンちゃんは怪人のことをたくさん話してくれた。
同じテレビを見ているはずなのに何故かとっても詳しかった。
しばらくふたりで仮面ライダーの世界に夢中になっていたが、少し飽きたぼくは提案した。
「ねぇ、ぼくん家にくる?」
「他の怪人持ってるの?」
「うん、あるよ」
「じゃ、行く」
家を出て角まで出ると、研ぎ屋のおじさんが店先で刃物を研いでいた。
店といっても看板がなければ、入り口がどこかもわからないような小さな掘っ立て小屋だった。
「シャッシャッ、シュー」
切り株のような台の上に載せた、灰色がかった緑色の四角い石にはホースから水がかかっていた。
おじさんが両手を使って砥石に擦り付けているのは鎌だった。
ノンちゃんの手にもカマキリ男が握られていた。
「シャー、シャー、シュッ」
やっぱりぼくはこの音が嫌いだ。
散髪屋さんの仕上げを思い出して、ざわわと鳥肌が立つ。
「はやく行こう、こっちだよ」
途中で偶然、ナオシに出くわしたので、ナオシも誘ってぼくたちは一緒に遊ぶことにした。
ピッツンはいなかった。
家に着くなり、ぼくは自分の人形をおもちゃ箱から出してふたりの前に披露した。
中でも今おもちゃ屋さんでは売り切れになっているコブラ男がぼくの自慢だった。
何といっても、コブラ男は普通のコブラの五万倍の毒を持っているのだ。
かわりばんこに仮面ライダー役になって、怪人を倒す遊びをした。
最後は必ずライダーキックで止めを刺す。
ナオシはとうとう自分自身が死神博士になって襲ってきたが、それならとこっちも自分の足で
ライダーキックを繰り出した。
新しいお友だちを連れてきたせいか、ばあちゃんがおやつを用意してくれたので、
ぼくは階下にそれを取りに行った。
器に山盛りの、切った柿と、ビスコがひとり二枚ずつ。
それを載せたお盆を持ってぼくは二階に引き返した。
もう散々遊んだので、ぼくたちはおやつに集中したけど、食べ終わるやいなやノンちゃんが帰ると言う。
「もう帰るの?」
「うん、また来るから」
家を出たところでバイバイと言おうとしたけど、ナオシもまだまだ物足りない様子だったので
ぼくは言った。
「もういっかいノンちゃんちで遊ばない?」
「え?」
「それがいい、それがいい、そうしよ」
ナオシはもう今にも死神博士に変身しそうだった。
なかば強引にぼくたちはノンちゃん家に押しかけたのだけど、何故かノンちゃんは元気がなさそうだった。
でも、いつもの様子といえばいつもの様子だ。
ところが、うしろについて階段を登っているとき、ノンちゃんの背中のシャツから何かがすべり出て、
階段の板の上にコトッと転がった。
コブラ男だった。
「ノンちゃん、落ちたよ」
「・・・・」
ぼくは右手で人形を拾って差し出したけど、何をどうしていいものか分からなかった。
ノンちゃんはうつむいて黙ったままで受け取らなかった。
こういう時は怒るのかなぁと思ったけど、腹は立っていないので怒ることはできなかった。
だけどぼくたちはお互いにバツが悪くなった。
だから、それこそ何が起きたのか分からないでいるナオシをうながして、ぼくは家を出た。
「どうしたの?」
「ううん、なんでもない」
「もう遊ばないの?」
「また明日ね」
研ぎ屋のおじさんはもういなかったけど、ホースの水は出しっぱなしだった。
砥石の上を滑らかにくにゃくにゃと流れる水の揺らぎがきれいだ。
そしてぼくはコブラ男をナオシに手渡しながらもう一度言った。
「また明日ね!」
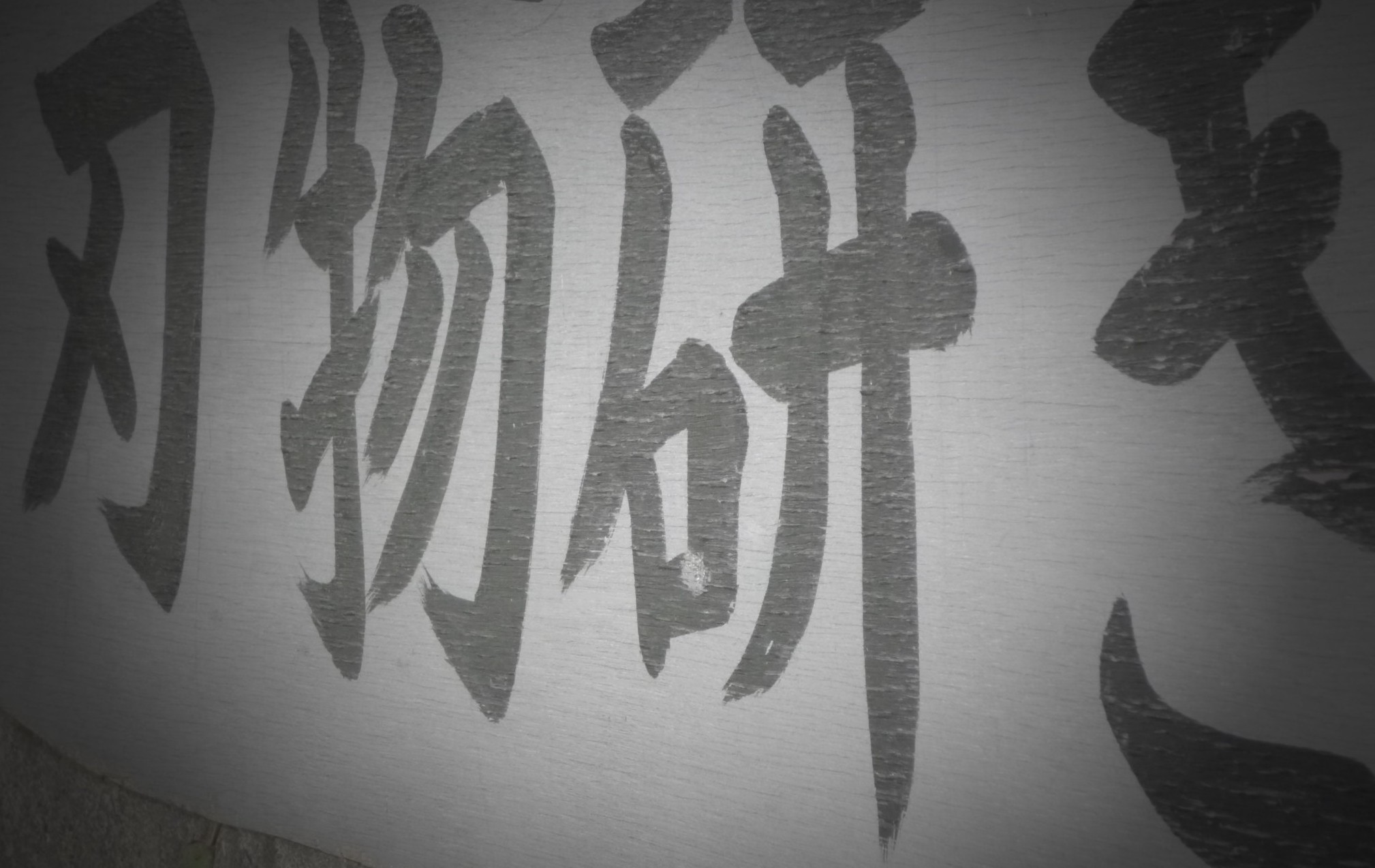
同じクラスにノリミチ君という子がいた。
まわりに太っている子はいないけど、その子は特に色が白くて痩せていた。
しかもおとなしくて動作も速くない。いや、とっても遅い。
みんなは「ノンちゃん」と呼んでいた。
ノンちゃんはどこか危なっかしくて、皆が気にかけてあげなくてはいけないような、
同級生なのに弟のような存在だった。
そんなノンちゃんとぼくはある日、突然接近することになった。
帰りの挨拶がおわって教室の出口に向かうぼくの視界に、ランドセルを背負おうとしている
ノンちゃんのゆっくりした動きが入ってきた。
一方の肩ベルトを腕に通して、もう一方に腕を通そうとして体をよじった瞬間、
ランドセルが傾いて、べろっと開いたフタの中から何かがボタッと床に落ちた。
学校には持ってきてはいけないオモチャ。塩ビというやわらかいプラスチックの人形。
それは仮面ライダーだった。
「あっ、これどうしたの?」
「家から持ってきた」
「持ってきたらだめだよ」
「でも持ってきた、持ってきただけ」
「早く隠しな」
「うん」
「ねぇ、他にも持ってるの?」
「うん、家にある」
「ねぇ、一緒に遊ぶ?」
「うん」
ぼくたちは連れ立って下校した。
家の方向が同じことがわかった。しかもノンちゃん家はぼくの通学路の途中にあった。
とぎ屋さんがある角から三軒目だった。
さっそく家にあがらせてもらって、ぼくは仮面ライダーの人形を見せてもらった。
怪人の人形も何体かあった。クモ男にカマキリ男。
無口なはずのノンちゃんは怪人のことをたくさん話してくれた。
同じテレビを見ているはずなのに何故かとっても詳しかった。
しばらくふたりで仮面ライダーの世界に夢中になっていたが、少し飽きたぼくは提案した。
「ねぇ、ぼくん家にくる?」
「他の怪人持ってるの?」
「うん、あるよ」
「じゃ、行く」
家を出て角まで出ると、研ぎ屋のおじさんが店先で刃物を研いでいた。
店といっても看板がなければ、入り口がどこかもわからないような小さな掘っ立て小屋だった。
「シャッシャッ、シュー」
切り株のような台の上に載せた、灰色がかった緑色の四角い石にはホースから水がかかっていた。
おじさんが両手を使って砥石に擦り付けているのは鎌だった。
ノンちゃんの手にもカマキリ男が握られていた。
「シャー、シャー、シュッ」
やっぱりぼくはこの音が嫌いだ。
散髪屋さんの仕上げを思い出して、ざわわと鳥肌が立つ。
「はやく行こう、こっちだよ」
途中で偶然、ナオシに出くわしたので、ナオシも誘ってぼくたちは一緒に遊ぶことにした。
ピッツンはいなかった。
家に着くなり、ぼくは自分の人形をおもちゃ箱から出してふたりの前に披露した。
中でも今おもちゃ屋さんでは売り切れになっているコブラ男がぼくの自慢だった。
何といっても、コブラ男は普通のコブラの五万倍の毒を持っているのだ。
かわりばんこに仮面ライダー役になって、怪人を倒す遊びをした。
最後は必ずライダーキックで止めを刺す。
ナオシはとうとう自分自身が死神博士になって襲ってきたが、それならとこっちも自分の足で
ライダーキックを繰り出した。
新しいお友だちを連れてきたせいか、ばあちゃんがおやつを用意してくれたので、
ぼくは階下にそれを取りに行った。
器に山盛りの、切った柿と、ビスコがひとり二枚ずつ。
それを載せたお盆を持ってぼくは二階に引き返した。
もう散々遊んだので、ぼくたちはおやつに集中したけど、食べ終わるやいなやノンちゃんが帰ると言う。
「もう帰るの?」
「うん、また来るから」
家を出たところでバイバイと言おうとしたけど、ナオシもまだまだ物足りない様子だったので
ぼくは言った。
「もういっかいノンちゃんちで遊ばない?」
「え?」
「それがいい、それがいい、そうしよ」
ナオシはもう今にも死神博士に変身しそうだった。
なかば強引にぼくたちはノンちゃん家に押しかけたのだけど、何故かノンちゃんは元気がなさそうだった。
でも、いつもの様子といえばいつもの様子だ。
ところが、うしろについて階段を登っているとき、ノンちゃんの背中のシャツから何かがすべり出て、
階段の板の上にコトッと転がった。
コブラ男だった。
「ノンちゃん、落ちたよ」
「・・・・」
ぼくは右手で人形を拾って差し出したけど、何をどうしていいものか分からなかった。
ノンちゃんはうつむいて黙ったままで受け取らなかった。
こういう時は怒るのかなぁと思ったけど、腹は立っていないので怒ることはできなかった。
だけどぼくたちはお互いにバツが悪くなった。
だから、それこそ何が起きたのか分からないでいるナオシをうながして、ぼくは家を出た。
「どうしたの?」
「ううん、なんでもない」
「もう遊ばないの?」
「また明日ね」
研ぎ屋のおじさんはもういなかったけど、ホースの水は出しっぱなしだった。
砥石の上を滑らかにくにゃくにゃと流れる水の揺らぎがきれいだ。
そしてぼくはコブラ男をナオシに手渡しながらもう一度言った。
「また明日ね!」
宝永町248番地 第66話 [Wessay]
白粉花
ぼくの家には犬と猫がいる。
大きな日本犬のレイと小柄な黒猫のタマだ。
タマの主人はぼくのつもりなんだけど、向こうはそう思っていないらしい。
せっかくエサをあげても、食べ終わるとすぐ立ち去って、
ちょっと離れたところで、何もなかったような態度で毛繕いをはじめる。
その仕草を観察するのは嫌いじゃなかったけど、
名前を呼んだら返事くらいしてもいいだろうとも思っていた。
そんなタマの姿がある日見えなくなった。
名前を呼んでもムダなのは知ってるけど、朝ごはんを作っておいても現れない。
ずっと待ってるわけにはいかないので、ぼくは学校に行った。
学校から帰ってきても、ごはんは中庭のいつもの場所にそのまま残っていた。
ちょっと心配だったけど、遊びの誘惑に負けて家を出て友だちを誘いに行った。
今日は何をしようかな?
夕方になってぼくたちの影が大人のように長くなると、おしろい花が咲き始める。
スズメ蛾がさっそく蜜を吸いに飛んでくる。
こいつを見かけるようになると夜が早くくる。
遊ぶ時間が短くなってくる。
ごはんができたよという、ばあちゃんの声を合図にぼくたちは家に帰った。
食卓につくなり、お父ちゃんにたずねた。
「ねぇ、タマがいないよ」
「そうか、そろそろかな」
「そろそろって何?」
「タマはもうだいぶ年寄りだからな」
「家に戻れなくなったの?」
「いや帰ってこれないんじゃない」
「じゃあどうして?」
「ネコはお別れするとき、自分から姿を消すんだよ、誰にも見つからないように」
「ええっ」
「きっともう帰ってこないな」
ぼくは「イヤだ」という言葉を飲み込んだけど、他の言葉も出てこなかった。
次の日の朝もタマは現れなかった。
下校するときに、ぼくは校庭にぽつんと立つイチョウの木に黄色い葉っぱを見つけた。
町もそろそろ秋という季節にすっぽりと包まれようとしている。
今日もふみちゃんたちと一緒に裏庭で遊んだ。
遊んでいる間はタマのことは忘れていた。
でも、おしろい花が咲いたのを見つけた瞬間、タマの声が聞こえたような気がした。
さよならって言えなかったけど、さよなら、タマ。
またいつか違うネコになって帰ってきてね。
色は黒じゃなくてもいいよ。タマの好きな色にして。
ぼくは猫の鼻先のような皺々の実を一粒とって、両手の指で半分に割った。
黒い種の中から出てきた真っ白なかたまりをさらに指先で潰した。
そして指についた白粉を、ふみちゃんの鼻の頭に、ちょこんと擦りつけてみた。

- この原稿を書いた翌日 2009.10.19 愛猫アス、永眠。 God bless him.
ぼくの家には犬と猫がいる。
大きな日本犬のレイと小柄な黒猫のタマだ。
タマの主人はぼくのつもりなんだけど、向こうはそう思っていないらしい。
せっかくエサをあげても、食べ終わるとすぐ立ち去って、
ちょっと離れたところで、何もなかったような態度で毛繕いをはじめる。
その仕草を観察するのは嫌いじゃなかったけど、
名前を呼んだら返事くらいしてもいいだろうとも思っていた。
そんなタマの姿がある日見えなくなった。
名前を呼んでもムダなのは知ってるけど、朝ごはんを作っておいても現れない。
ずっと待ってるわけにはいかないので、ぼくは学校に行った。
学校から帰ってきても、ごはんは中庭のいつもの場所にそのまま残っていた。
ちょっと心配だったけど、遊びの誘惑に負けて家を出て友だちを誘いに行った。
今日は何をしようかな?
夕方になってぼくたちの影が大人のように長くなると、おしろい花が咲き始める。
スズメ蛾がさっそく蜜を吸いに飛んでくる。
こいつを見かけるようになると夜が早くくる。
遊ぶ時間が短くなってくる。
ごはんができたよという、ばあちゃんの声を合図にぼくたちは家に帰った。
食卓につくなり、お父ちゃんにたずねた。
「ねぇ、タマがいないよ」
「そうか、そろそろかな」
「そろそろって何?」
「タマはもうだいぶ年寄りだからな」
「家に戻れなくなったの?」
「いや帰ってこれないんじゃない」
「じゃあどうして?」
「ネコはお別れするとき、自分から姿を消すんだよ、誰にも見つからないように」
「ええっ」
「きっともう帰ってこないな」
ぼくは「イヤだ」という言葉を飲み込んだけど、他の言葉も出てこなかった。
次の日の朝もタマは現れなかった。
下校するときに、ぼくは校庭にぽつんと立つイチョウの木に黄色い葉っぱを見つけた。
町もそろそろ秋という季節にすっぽりと包まれようとしている。
今日もふみちゃんたちと一緒に裏庭で遊んだ。
遊んでいる間はタマのことは忘れていた。
でも、おしろい花が咲いたのを見つけた瞬間、タマの声が聞こえたような気がした。
さよならって言えなかったけど、さよなら、タマ。
またいつか違うネコになって帰ってきてね。
色は黒じゃなくてもいいよ。タマの好きな色にして。
ぼくは猫の鼻先のような皺々の実を一粒とって、両手の指で半分に割った。
黒い種の中から出てきた真っ白なかたまりをさらに指先で潰した。
そして指についた白粉を、ふみちゃんの鼻の頭に、ちょこんと擦りつけてみた。
- この原稿を書いた翌日 2009.10.19 愛猫アス、永眠。 God bless him.
宝永町248番地 第65話 [Wessay]
おたふく風邪
ぼくは眉毛のところにキズがある。
もっとぼくが小さい頃、幼稚園に行きはじめる前だったと思うけど、
お父ちゃんがぼくを抱いたまま階段を下りようとしていた時、
酔っ払っていたのか、足を踏み外して転げ落ちたのだ。
その階段は鉄でできているので、むしろ、よくかすり傷ですんだものだと思う。
お父ちゃんがどんな怪我をしたのかは知らないけど。
ところで、ぼくは鼻が悪い。風邪をひいてなくても鼻水がいっぱいでる。
月に一度、病院の「じびいんこう科」というところに行って、薬を吸引している。
ばあちゃんが言うには「ちくのう」なのだそうだ。
どんな病気かはよくわからないけど、ぼくがちくのうなら、お友だちもみんなちくのうに見える。
妹はちくのうには見えなかったけど、熱を出した。
相当熱が高かったので、お母ちゃんが商店街の中にある大木医院へ連れて行った。
帰ってきた二人を店先でばあちゃんが迎えて聞いた。
「どう?」
「おたふく風邪だって」
ぼくはそのへんてこな名前に興味を持った。
「オタフクって福笑いのオタフク?」
「まぁそうだけど、普通の風邪とはちがうのよ」
「ふうん」
なんとなく妹の顔がオタフクに見えなくもないが、
もともと真ん丸い顔だし、病気の影響がどれだけなのか、ぼくにはよくわからなかった。
でも、ふうふうと熱に浮かされている様子は苦しそうで可哀想だった。
それから二日後、妹は見事に快復した。
あんなにしんどそうだったのが嘘のように、いつもの短いワンピースで走り回っている。
一方、ぼくは熱が出た。伝染ったらしい。
大人たちはしばらく様子を見ていたようだが、おぼろげな意識の中で
布団のそばにいるばあちゃんとお母ちゃんの話を聞いていると、
熱は下がるどころかじわじわ上がっているようだった。
夜半にもかかわらず、お母ちゃんはぼくを抱いて大木医院の玄関の呼び鈴を押した。
ぼくはそのまま一晩中看護されたようだった。
明くる朝、少し正気を取り戻したぼくにお母ちゃんが声をかけた。
「目が覚めたか、よかったよかった、もう大丈夫よ」
取り囲むみんなの表情から察するに、そうとう重篤だったようだ。
片方の耳には、中耳炎になった子がするヘッドホンの片割れみたいなのが宛がわれていた。
何がおこったのかはわからないけど、妹のことを恨めしく思う気持ちがこみ上げてきた。
夕方、お母ちゃんが迎えに来てくれて、やっと病院を後にすることができた。
家までもどると、店先でばあちゃんが迎えて聞いた。
「どうや?」
「もう大丈夫だけど、ひとつ間違ったら大事になるところだったよ」
「そうか、でもよかったよかった」
「ばい菌が耳にまで行って、もうちょっとで脳みそまで行くところだったみたい」
「そうかそうか、もうちょっとでパーになってたか、そうかそうか」
パーにはなりたくないと思った。
でも今、自分がパーじゃないって、どうして言えるんだろうとも考えた。
考えたけど、よくわからない。よくわからないのはパーだからかもしれない。
でもまぁ、それならそれでしようがない。
みんなとまたハナを垂れながら遊べればそれでいい。
あしたは遊べるかな?あさってなら多分大丈夫かな?
しいちゃんとまっちゃんもかわりばんこに様子を見に来てくれた。
こういうのも悪くない。ここは大人しくじっと寝てよう。
そしてその数日後、酔っ払って帰ってきたお父ちゃんは妹を風呂に入れようと
抱っこしたまま階段を降りようとして足を踏み外した。
今度は妹の眉毛にキズができた。

ぼくは眉毛のところにキズがある。
もっとぼくが小さい頃、幼稚園に行きはじめる前だったと思うけど、
お父ちゃんがぼくを抱いたまま階段を下りようとしていた時、
酔っ払っていたのか、足を踏み外して転げ落ちたのだ。
その階段は鉄でできているので、むしろ、よくかすり傷ですんだものだと思う。
お父ちゃんがどんな怪我をしたのかは知らないけど。
ところで、ぼくは鼻が悪い。風邪をひいてなくても鼻水がいっぱいでる。
月に一度、病院の「じびいんこう科」というところに行って、薬を吸引している。
ばあちゃんが言うには「ちくのう」なのだそうだ。
どんな病気かはよくわからないけど、ぼくがちくのうなら、お友だちもみんなちくのうに見える。
妹はちくのうには見えなかったけど、熱を出した。
相当熱が高かったので、お母ちゃんが商店街の中にある大木医院へ連れて行った。
帰ってきた二人を店先でばあちゃんが迎えて聞いた。
「どう?」
「おたふく風邪だって」
ぼくはそのへんてこな名前に興味を持った。
「オタフクって福笑いのオタフク?」
「まぁそうだけど、普通の風邪とはちがうのよ」
「ふうん」
なんとなく妹の顔がオタフクに見えなくもないが、
もともと真ん丸い顔だし、病気の影響がどれだけなのか、ぼくにはよくわからなかった。
でも、ふうふうと熱に浮かされている様子は苦しそうで可哀想だった。
それから二日後、妹は見事に快復した。
あんなにしんどそうだったのが嘘のように、いつもの短いワンピースで走り回っている。
一方、ぼくは熱が出た。伝染ったらしい。
大人たちはしばらく様子を見ていたようだが、おぼろげな意識の中で
布団のそばにいるばあちゃんとお母ちゃんの話を聞いていると、
熱は下がるどころかじわじわ上がっているようだった。
夜半にもかかわらず、お母ちゃんはぼくを抱いて大木医院の玄関の呼び鈴を押した。
ぼくはそのまま一晩中看護されたようだった。
明くる朝、少し正気を取り戻したぼくにお母ちゃんが声をかけた。
「目が覚めたか、よかったよかった、もう大丈夫よ」
取り囲むみんなの表情から察するに、そうとう重篤だったようだ。
片方の耳には、中耳炎になった子がするヘッドホンの片割れみたいなのが宛がわれていた。
何がおこったのかはわからないけど、妹のことを恨めしく思う気持ちがこみ上げてきた。
夕方、お母ちゃんが迎えに来てくれて、やっと病院を後にすることができた。
家までもどると、店先でばあちゃんが迎えて聞いた。
「どうや?」
「もう大丈夫だけど、ひとつ間違ったら大事になるところだったよ」
「そうか、でもよかったよかった」
「ばい菌が耳にまで行って、もうちょっとで脳みそまで行くところだったみたい」
「そうかそうか、もうちょっとでパーになってたか、そうかそうか」
パーにはなりたくないと思った。
でも今、自分がパーじゃないって、どうして言えるんだろうとも考えた。
考えたけど、よくわからない。よくわからないのはパーだからかもしれない。
でもまぁ、それならそれでしようがない。
みんなとまたハナを垂れながら遊べればそれでいい。
あしたは遊べるかな?あさってなら多分大丈夫かな?
しいちゃんとまっちゃんもかわりばんこに様子を見に来てくれた。
こういうのも悪くない。ここは大人しくじっと寝てよう。
そしてその数日後、酔っ払って帰ってきたお父ちゃんは妹を風呂に入れようと
抱っこしたまま階段を降りようとして足を踏み外した。
今度は妹の眉毛にキズができた。
前の10件 | -



